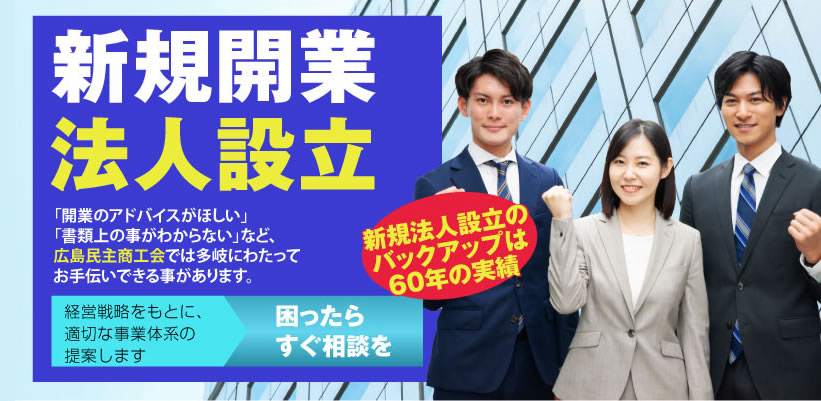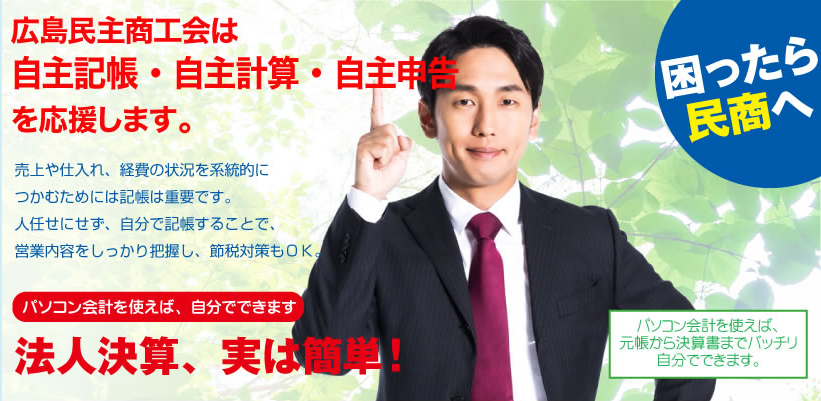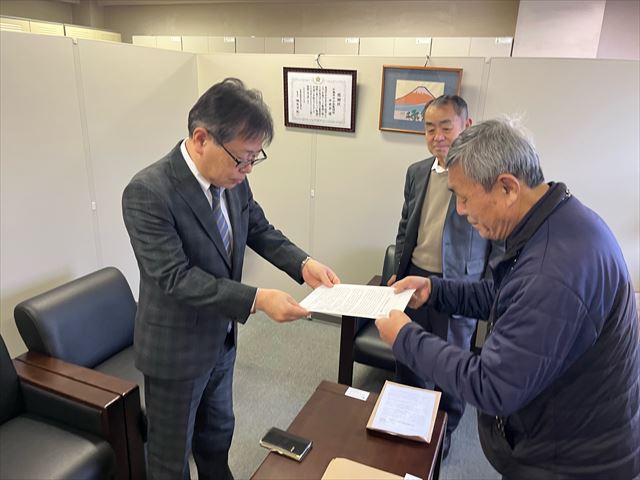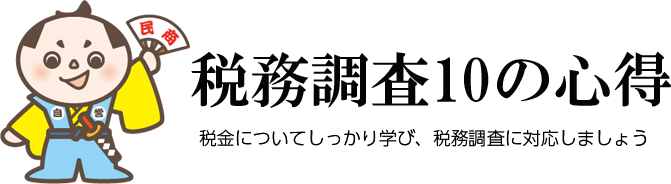全国で所有者不明土地が増えており、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策の公共事業の妨げになるなど社会問題になっています。
こうした問題を解消するため、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられました。
施行以前に相続で取得した不動産も対象です。
Q令和6年4月1日より前に相続した不動産はどうなるの?
A4月1日より前に相続した不動産も対象となります。その場合の期限は施行日の令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)となります。
Q登記せずに放っておくとどうなるの?
A正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
Q3年以内に相続登記を申請することができない場合はどうすればいいの?
A今回新しく、「相続人申告登記」の制度が創設されました。自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができる制度です。自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出するだけでひとまず簡易に手続を行うことができますが、いずれは登記をしないといけません。
Q田舎の土地で使い道がなく、誰も相続したがらない。手放したいけれど引き取り手もなく、処分に困っている…。
A所有者不明土地の発生を予防するため、土地を相続した方が不要な土地を手放して国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」(令和5年4月27日施行)が設けられています。今後の固定資産税等を考えると引き渡した方がいいかもしれません。相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、どなたでも申請可能です(売買等で土地を取得した方や法人は対象外)。国に引き渡すためには、法務大臣(窓口は法務局)の承認を得た上で、10年分の土地管理費相当額を納付する必要があります。土地が共有地である場合には、共有者全員で申請となります。
QDV被害者のため、住所が分かると困るので登記したくない・・
ADV被害者等を保護するため、登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例も新たに設けられました。
これからの法改正も
★親の不動産がどこにあるか調べられる「所有不動産記録証明制度」(令和8年2月2日施行)
★他の公的機関との情報連携により所有権の登記名義人の住所等が変わったら不動産登記にも反映されるようになる仕組み(令和8年4月1日施行)。
★住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行)。登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要が出てきます。なお、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料の適用対象となる。
今後の制度改正もチェックしていきましょう。